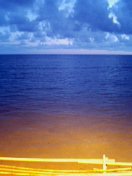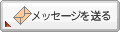2005年11月26日/ シンポジウム「沖縄の詩の現在」
報告(5) 天沢退ニ郎氏
 ようやく第一部の最後、天沢退二郎氏のお話についてです。氏のお話は、レジュメを伴った報告の形ではなく、ご自身の体験が語られるという形でなされました。
ようやく第一部の最後、天沢退二郎氏のお話についてです。氏のお話は、レジュメを伴った報告の形ではなく、ご自身の体験が語られるという形でなされました。「私と沖縄とのつながりは、吉増剛三氏の後をお受けして山之口貘賞の選考委員の末席を汚したことで・・・・・・」「今までのお話を聞いていて、自分もこの場にいていいのか、と恐縮する思いがいたしました」と、謙遜しつつ語り始められた天沢氏。まず、満洲での幼少時の体験から語られたことは、データとして資料に示された氏のプロフィールに色を甦らせ、会場をぐっと引き込んだ気がしました。
お話の柱は、前回ご紹介した宮城氏の記事にもまとめられている通り、貘賞選考の際の体験談でした。氏は、まず「沖縄は割を食っている」と述べられたあと、次のように語られました。
「これまで色々な賞の選考委員を経験しましたが、貘賞の性質はそのいずれとも異なるものでした。それは、おそらく応募される詩集の性質によるものであり、貘賞への応募詩集には、受賞に推せるものとは違うのだけれども、選考委員全員が衝撃を受ける、そういう詩集が必ずあります。そのことで僕は、詩を書くことで生きようとしている、そのような方々が沖縄の詩を支えているということを、強く感じました」
(天沢氏の声を思い出しながら再現してみましたが、細かいところは、実際に語られた言葉とは違っていると思います。あしからず。)
この見解は非常に共感を呼び、第2部のディスカッションでも触れられました。宮城氏は、「自分にとって詩作は実際に心の支えとなっていた」と述懐、コメンテーターの大野氏も、「(賞の選考の際に)落とすと決めながら、自分は何をしているんだろう、という気持ちになることがあります・・・・・・」と打ち明けられる場面もありました。
朗読は、天沢氏はなさらなかったと思います(実はこの辺りからじわじわと頭痛に襲われてしまったせいか、記憶があやふやな上にメモもないので、もし違っていたら、参加なさった方のご指摘をお願いいたします)。
ところで、来る12月3日の土曜日、天沢氏も参加されるポエトリーリーディングのイベントが催されます。またも明治学院大学にて。このイベントには、宮城氏とともに沖国大の文芸部で活動されていた詩人トーマ・ヒロコ氏(詩誌「1999」同人)も参加されるようです。詳細は以下でご確認ください。
ポエトリーリーディング 現代詩に声を取り戻そう
(写真: 夕鶴。東京の自宅近くにて)
Posted by あゆ at 07:00│Comments(6)
この記事へのコメント
呼ばれたような気がしたので来てみました(笑)
では僕の記憶から補足を・・・・・・と言いたいところですが、
やっぱり同じような所が印象に残るものなんですねえ。
ちょうど僕が覚えていたことが、全部書かれてます(^^;)
では僕の記憶から補足を・・・・・・と言いたいところですが、
やっぱり同じような所が印象に残るものなんですねえ。
ちょうど僕が覚えていたことが、全部書かれてます(^^;)
Posted by 茶太郎 at 2005年11月27日 16:21
あら、そうでしたか! まあでも、事実と違うことは書いてなかったようで安心しました。
次回あたり、そろそろ茶太郎さんの出番です(笑)
次回あたり、そろそろ茶太郎さんの出番です(笑)
Posted by あゆ at 2005年11月27日 19:56
うらやましいと言ってしまいたくないのですが、刺激的なイベントが次々開かれる、さすが東京だなぁと思います。
自分がいた頃には、毎週のように飲み歩いて疲れ切ってしまったのですけれど(苦笑)
頭痛、だいじょうぶでした?・・・刺激的すぎました?^^;
自分がいた頃には、毎週のように飲み歩いて疲れ切ってしまったのですけれど(苦笑)
頭痛、だいじょうぶでした?・・・刺激的すぎました?^^;
Posted by びん at 2005年11月28日 11:56
確かに・・・でも最近、遠くて行けないイベントなどがあると、刺激的なことってあちこちにあるなあと実感することも多いですね。
シンポジウム、話も面白かったのに加え、はりきりすぎてかなり前列に陣取ってしまったので、どの点から考えても全く気が抜けず、強烈すぎる体験だったかもしれません(笑)
シンポジウム、話も面白かったのに加え、はりきりすぎてかなり前列に陣取ってしまったので、どの点から考えても全く気が抜けず、強烈すぎる体験だったかもしれません(笑)
Posted by あゆ at 2005年11月28日 13:39
八重山に海に咲く花があります。海草ではなく陸性の植物です。「塩の害」を克服しても子孫のためには受粉という作業を海の上で風にたよりつつ行わなければいけません。花粉には湿度が大敵ですが、見事な防水機構を作って受粉を成功させ今も海の上で白い花を咲かせています。植物のイルカは何故この道をたどったのか?サボテンが葉を厚くして水分の蓄えに対応したという適応力を超えている感じがするのです。植物には企画開発部にあたる脳のようなセンターがありません。頭がないのに頭がいい。そうするとアカバナアも植物知能を発揮して人に対応したのではないか?ぎんぎん、ぎらぎら夕日が沈み、だんだんくらしんがやってくる。まっくらしんの時、恐怖と魅惑の共同体が包まれる。アカバナアはそこの転換点に目をつけ、人が欲するに違いない花の色と形を提供した。そして無謀にも種はいらないと思ったとき、何事かの成就を知らしめんがため、種をつくるという根本的な「地上での永遠」という衝動さえぐらつかせることに成功した。超古よりさし木でいきつづけているアカバナア。ただしアカバナアの葉ではおしりを拭くには小さすぎます。そこはユナンギーが人にちゃんとおしりふきの大きさの葉を提供しています。沖縄のお箸の赤と黄色はアカバナアとユナンギーが天然の対象物ですが、あの世とこの世の象徴にもなっている。ここにしか咲かない花はユイムンアカバナア。ここに咲く花は在来ユナンギー。沖縄にはみっつのミステリーがあります。アカバナアミステリー、渡り蝶のミステリー、グスクミステリー、どれもユイムンという特徴があります。スクで時宣をえてスクスク育つ沖縄、何もないところに降り立つはビシュヌ。この話をどう考えますか?
10年前アムロナミエはデビユーした。ナミエの背後には大物プロデュサーS氏が絡んでいるという。S氏は次に中島みゆきを魅惑のベールに包み、彼女をいっそうの引きこもりにさせた。3部作ヘッドライト、地上の星、銀の龍はベール内の情緒によって創られた。ナミエが人気したとき、アムラー、シノラーという語尾長音という流行をつくったが、彼女のデビューは「トゥライミー」という題名だった。ミーはミーイズムのミーではなく、日本の音のミーととらえなければいけない。彼女は腰を鋭角的にキュ、キュと動かせることが特徴だった。今にして思うと、当時なんの理解もなくただガマクナミエとあだ名したものだが、G音に気をつけて!というシグナルだったのだ。G音がグーを探し当て、ギンギン、と
いう貴重な音の解明につながった。擬態語の耳グスグスは沖縄の立場を象徴しているし、グサリとやると日本の擬態語にもなる。ガンガン、ギンギン、グングン、ビシュヌは世界再編工作を続けている。飲む、打つ、買う三拍子そろった達人吉行淳之介氏にはほれぼれするほどの繊細な魅力がある。修羅場で濡れ場で彼の聖性は活躍した。彼が絶好調のときはホステスの女の名前をすべて当てたという。セイントヨシユキはこの世への花向けの言葉をぽつりと言い終わって辞世した。「島尾敏尾の方から光が見える」
アカバナアに語ることができ、カラダが動き出す人を詩人という。
私では戸口までなのでだめだ。我こそはと思うものは語りかけ、アカバナアダンサーが輩出して欲しい。
10年前アムロナミエはデビユーした。ナミエの背後には大物プロデュサーS氏が絡んでいるという。S氏は次に中島みゆきを魅惑のベールに包み、彼女をいっそうの引きこもりにさせた。3部作ヘッドライト、地上の星、銀の龍はベール内の情緒によって創られた。ナミエが人気したとき、アムラー、シノラーという語尾長音という流行をつくったが、彼女のデビューは「トゥライミー」という題名だった。ミーはミーイズムのミーではなく、日本の音のミーととらえなければいけない。彼女は腰を鋭角的にキュ、キュと動かせることが特徴だった。今にして思うと、当時なんの理解もなくただガマクナミエとあだ名したものだが、G音に気をつけて!というシグナルだったのだ。G音がグーを探し当て、ギンギン、と
いう貴重な音の解明につながった。擬態語の耳グスグスは沖縄の立場を象徴しているし、グサリとやると日本の擬態語にもなる。ガンガン、ギンギン、グングン、ビシュヌは世界再編工作を続けている。飲む、打つ、買う三拍子そろった達人吉行淳之介氏にはほれぼれするほどの繊細な魅力がある。修羅場で濡れ場で彼の聖性は活躍した。彼が絶好調のときはホステスの女の名前をすべて当てたという。セイントヨシユキはこの世への花向けの言葉をぽつりと言い終わって辞世した。「島尾敏尾の方から光が見える」
アカバナアに語ることができ、カラダが動き出す人を詩人という。
私では戸口までなのでだめだ。我こそはと思うものは語りかけ、アカバナアダンサーが輩出して欲しい。
Posted by ガジャン at 2005年11月28日 15:34
ガジャンさん、いつも関心を持ってくださり、ありがとうございます。
コメントをお寄せくださることは嬉しいのですが、長さと、コメントとして散在させるには惜しい内容から、この機会にブログをお作りになってみてはいかがかと僭越ながら思いました。
生ぬるいブログかと思いますが、これからもよろしくお願いいたします。
コメントをお寄せくださることは嬉しいのですが、長さと、コメントとして散在させるには惜しい内容から、この機会にブログをお作りになってみてはいかがかと僭越ながら思いました。
生ぬるいブログかと思いますが、これからもよろしくお願いいたします。
Posted by あゆ at 2005年11月28日 15:50